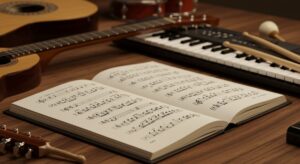同主調転調の基本を知ろう

同主調転調は、楽曲に新たな表情を加える方法のひとつです。初心者でも理解しやすいポイントを押さえて解説します。
同主調とは中心音が同じ異なる調のこと
同主調とは、中心となる音(主音)は同じまま、長調と短調を切り替える調の関係を指します。たとえば「ハ長調」と「ハ短調」は、どちらも中心の音が「ド」であるため同主調にあたります。
この関係を表にまとめると、以下のようになります。
| 長調(メジャー) | 短調(マイナー) | 主音(中心音) |
|---|---|---|
| ハ長調 | ハ短調 | ド |
| ト長調 | ト短調 | ソ |
| イ長調 | イ短調 | ラ |
同主調は、曲の途中で雰囲気を変えたいときによく使われます。中心音が変わらないため、転調しても違和感が少なく、聴き手にも親しみやすい特徴があります。
同主調転調が楽曲に与える印象の変化
同主調転調を使うと、曲の明るさや暗さがはっきりと入れ替わる印象が生まれます。たとえば、長調から短調に転調すると、明るくポジティブな雰囲気が一気に落ち着いた印象に変わることが多いです。
一方、短調から長調に転調する場合は、しっとりとした雰囲気から明るい希望を感じる展開につながります。このように、同主調転調は楽曲の世界観やストーリーを強調したいときに効果的に使えます。
同主調転調が使われる理由とメリット
同主調転調が重宝される理由は、曲全体のまとまりを保ちながら変化をつけやすい点にあります。中心音が変わらないため、メロディや歌詞の一部をそのまま活用でき、編曲のバリエーションも広がります。
また、聴き手にとっても転調後の違和感が少ないため、自然に受け入れやすいです。気分転換やサビなど印象を強めたい場面で効果的に使われており、多くのジャンルで活躍しています。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!
同主調転調のやり方とコツ

ここでは、実際に同主調転調を行う手順や、スムーズに転調するためのポイントを紹介します。
長調から短調への同主調転調の方法
長調から同じ主音の短調に転調する際は、まず現在の調(たとえばハ長調=Cメジャー)の主音を意識しましょう。転調先(ハ短調=Cマイナー)では、3つの音が変化します。具体的には、E→E♭、A→A♭、B→B♭となります。
和音進行を工夫すると、より自然に転調できます。たとえば、CメジャーからCマイナーへは、G7(ソ・シ・レ・ファ)を弾いた後、Cマイナー(ド・ミ♭・ソ)へ進む方法が一般的です。こうした進行を使うことで、メロディや伴奏のつながりが滑らかになります。
短調から長調への同主調転調の方法
短調から長調への転調では、短調特有の暗い響きが、一気に明るく変化します。たとえば、イ短調(Aマイナー)からイ長調(Aメジャー)へ転調する場合、C、D、Gなどの和音を経由し、最後にAメジャーに進むと効果的です。
このとき、短調で使われていた♭(フラット)が消え、シャープやナチュラルの音が登場します。移行部分で両方の和音を使うことで、聴き手に自然な転調感を与えることができます。
スムーズに転調するためのテクニック
同主調転調を滑らかに使いたい場合、共通音や共通和音を活用します。たとえば、CメジャーとCマイナーの共通音である「ド」や「ソ」をメロディや伴奏に残しておくと、急激な変化を和らげることができます。
また、一度ドミナント(GやEなどの5度の和音)を挟んでから転調する方法や、メロディの繰り返し部分に合わせて転調する方法も有効です。これらのテクニックを使うと、転調部分だけが浮くのを避け、曲全体に統一感を持たせることができます。
ポップスやJPOPでの同主調転調の実例

多くのポップスやJPOPで、同主調転調はさりげなく取り入れられています。代表的な楽曲やその特徴を見ていきましょう。
有名曲での同主調転調の使われ方
有名なJPOPや洋楽の中には、サビや大サビで同主調転調が使われている例が多くあります。たとえば、イントロやAメロでは長調で進み、サビで短調に転調することで、曲の展開にドラマチックな起伏を与えています。
また、エンディング部分で短調から長調に転調することで、感動や希望を感じさせるパターンも多いです。同主調転調は曲の構成を印象づける役割を持ち、ヒット曲でもよく活用されています。
ヒットソングから学ぶ転調パターン
ヒットソングの転調パターンは、大きく3つのタイプに分けられます。
- AメロやBメロとサビで転調が使われる
- サビの後半だけ転調する
- アウトロやエンディングで転調する
たとえば、Aメロで長調→サビで短調、またはその逆、などパターンはさまざまです。曲の盛り上がりやメッセージによって、同主調転調のタイミングや使い方が変化しているのがわかります。
曲作りに生かせる同主調転調の応用例
作曲やアレンジの際、同主調転調は表現力を高める手段です。たとえば、歌詞の内容が変化する場面で転調すれば、感情の流れを音楽でサポートできます。
また、バンド演奏では、ギターやキーボードが同じ形のフレーズを保ちながら転調できるため、演奏の負担が少ないという利点もあります。シンプルな楽曲でも、同主調転調を入れることで奥行きやメリハリを出すことができます。
他の転調手法との違いと組み合わせ

同主調転調以外にも多様な転調方法が存在します。それぞれの特徴や組み合わせ方を理解しましょう。
平行調転調との違いと使い分け
平行調転調は、同じ調号を持つ長調と短調の間で転調する方法です。たとえば、ハ長調(Cメジャー)とイ短調(Aマイナー)は平行調です。対して、同主調は主音が同じという違いがあります。
平行調転調は音階の雰囲気を大きく変えずに転調できるため、自然な流れが出しやすいです。同主調転調は主音の一貫性を保ったまま、曲調をがらりと変えたいときに適しています。曲の展開や伝えたい感情によって、使い分けるのがポイントです。
セカンダリードミナントを使った転調
セカンダリードミナントは、転調先の新しい調の5度の和音(ドミナント)を使って転調するテクニックです。たとえば、CメジャーからFメジャーに転調したい場合、一度Cメジャー上でC7を弾いてからFメジャーに進むようにします。
この方法を使うと、次の調に自然に移行できるため、同主調転調と組み合わせると、より洗練された転調が可能です。難しく感じた場合は、まずシンプルなパターンから試してみると良いでしょう。
他の転調手法と同主調転調の組み合わせ方
同主調転調は、他の転調手法と組み合わせて使うことで、楽曲に深みを加えることができます。たとえば、Aメロで平行調、Bメロで同主調、サビでセカンダリードミナントを使うなど、複数の転調を組み込むことで曲の表情がより豊かになります。
組み合わせる場合は、流れが不自然にならないよう、共通音や共通和音を意識しながら進行を設計することが大切です。実際のヒット曲でも、複数の転調テクニックを融合している例が多く見られます。
まとめ:同主調転調で音楽表現の幅を広げよう
同主調転調は、中心音を変えずに楽曲の雰囲気を大きく変化させる有効な方法です。ポップスやJPOPでもよく使われており、作曲やアレンジの幅を広げてくれます。
初心者でも取り入れやすい手法なので、ぜひ自分の曲作りやバンド演奏に取り入れてみてください。音楽表現の可能性がさらに広がります。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!