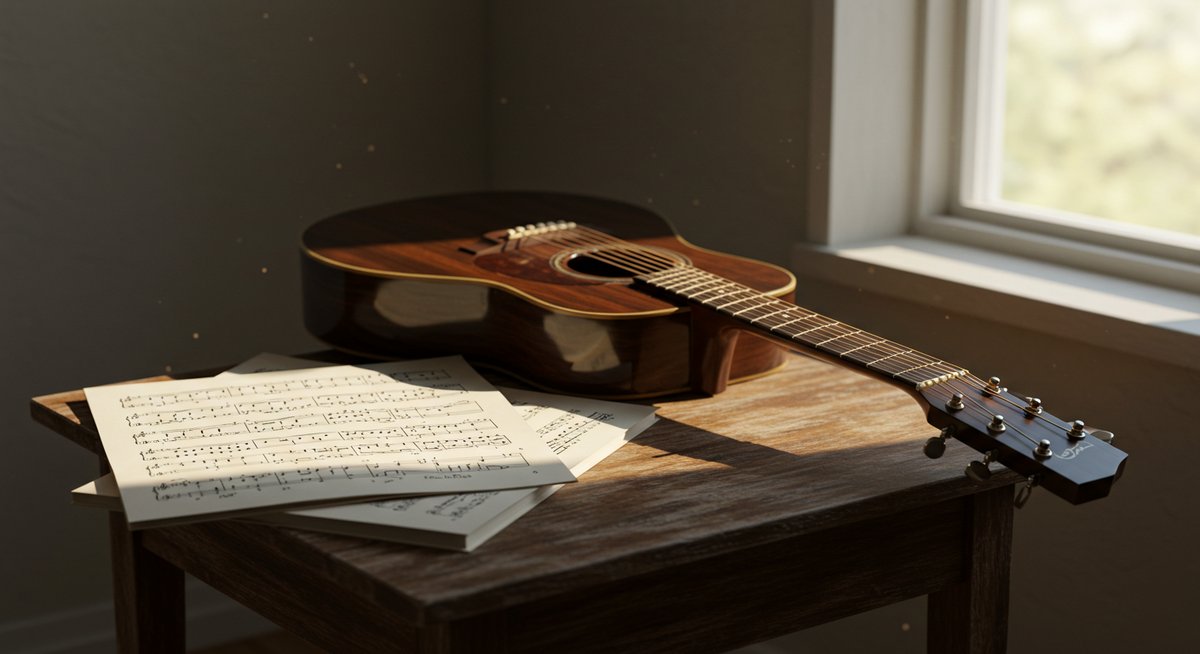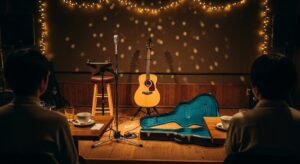カバー曲と著作権の基礎知識をわかりやすく解説
バンド活動や音楽配信を始めると、カバー曲や著作権について気になる方が多いのではないでしょうか。ここでは基本的なポイントをわかりやすく解説します。
カバー曲とは原曲との違いや定義
カバー曲とは、誰かが作った楽曲を別のアーティストやバンドが自分なりに演奏・録音して発表するものです。原曲はその曲を最初に制作・発表した人やグループの演奏や歌唱によるバージョンを指します。
たとえば、有名なポップソングを別のバンドがアレンジして演奏する場合、その演奏はカバー曲となります。カバー曲は、原曲の雰囲気を残したまま別の解釈を加えたり、ジャンルを変えて表現されることも多いです。日本では「コピー曲」と呼ばれることもありますが、基本的には同じ意味で使われています。
著作権が及ぶ範囲とカバー演奏の注意点
音楽には「著作権」という権利があり、作詞家や作曲家などの権利者が曲の利用方法をコントロールしています。カバー演奏をする際には、この著作権がどこまで及ぶのかを理解することが大切です。
たとえば、ライブハウスでの演奏であれば会場側が著作権料を支払っている場合もありますが、路上ライブや動画配信では演奏者自身が手続きをしなければならない場合もあります。カバー曲を無断で公の場で使うと、著作権侵害となるリスクがあるため注意が必要です。
著作権管理団体JASRACとNexToneの役割
日本の著作権管理団体には、JASRAC(日本音楽著作権協会)とNexToneがあります。これらの団体は、楽曲の著作権を管理し、使用料を集めて権利者に分配する役割を担っています。
JASRACは国内でもっとも大きな著作権管理団体で、幅広いジャンルの楽曲を管理しています。NexToneは新しい形の管理団体として設立され、主にデジタル配信などの分野で活躍しています。利用したい楽曲がどちらの団体で管理されているかを確認することが、カバー演奏や配信の際に重要となります。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!
カバー曲を演奏配信する際に必要な著作権手続き
SNSやYouTubeなどでカバー曲を演奏・配信する場合、著作権の手続きが求められることがあります。ここでは必要な調査や手続きの方法について説明します。
原曲の著作権管理状況を調べる方法
カバーしたい曲がどの著作権管理団体に登録されているかを調べることは大切です。管理団体によって手続き方法が異なるため、事前に調査しておくとトラブルを避けられます。
調べ方の一例を紹介します。
- JASRACの公式サイトで「作品データベース検索サービス(J-WID)」を利用
- NexToneの「作品検索」ページで検索
これらの検索サービスで曲名やアーティスト名を入力すると、管理団体や権利状況を確認できます。もし管理されていない場合は、作詞・作曲者に直接確認が必要です。
自己管理楽曲と著作権管理事業者管理楽曲の違い
楽曲の著作権には、「自己管理楽曲」と「著作権管理事業者管理楽曲」の2つのパターンがあります。自己管理楽曲は、作家本人や権利者自身が直接管理しており、利用許可も本人から得ることになります。
一方で、著作権管理事業者管理楽曲は、JASRACやNexToneなどの団体が管理しており、団体を通じて使用許可を取得します。たとえば、インディーズアーティストのオリジナル曲は自己管理の場合が多く、有名な楽曲ほど管理事業者が関わるケースが増えます。
この違いをしっかり把握し、自分が利用したい楽曲がどちらで管理されているのか調べてから手続きに進みましょう。
配信やYouTube投稿時に必要な許諾とは
カバー曲をYouTubeやSNSなどで配信する場合、著作権管理団体から「配信許諾」が必要となる場合があります。許諾の種類によっては申請が不要なケースもありますが、事前確認が重要です。
たとえば、YouTubeはJASRACやNexToneと包括契約を結んでいるため、多くの楽曲は自分で申請しなくても配信できます。ただし、すべての曲が対象ではないため、管理団体のデータベースで配信許諾の有無を確認しましょう。また、動画内で原曲の音源を利用する場合や収益化を希望する時は、追加の手続きや権利者への連絡が必要になることもあります。
路上ライブやイベントでカバー曲を演奏する時の注意点
路上ライブや各種イベントでカバー曲を演奏する際にも、著作権について注意すべき点があります。状況に応じた手続きを知って安心して演奏を楽しみましょう。
路上ライブでのカバー演奏と著作権侵害リスク
路上ライブでカバー曲を演奏する場合、著作権管理団体への利用申請が必要になることがあります。公共の場所での演奏は「公衆に聞かせるための利用」となり、著作権の対象となるためです。
また、都道府県や市区町村によっては、路上ライブ自体に許可が必要な場合もあります。著作権以外にも、場所ごとのルールやマナーを守ることが求められます。無許可で演奏した場合、著作権侵害とみなされるリスクがあるので、演奏前に管理団体や自治体に確認することをおすすめします。
投げ銭やCD販売時の著作権クリア方法
路上ライブで投げ銭を受け取ったり、カバーCDを販売したりする際には、追加で著作権手続きが必要です。営利目的とみなされるため、権利者や管理団体への申請が求められる場合があります。
実際の手続きとしては、JASRACやNexToneに申請を行い、必要な使用料を支払うことが一般的です。また、自己管理楽曲の場合は権利者本人の許可が必要となります。下記のようなケースごとに対応が異なるため注意しましょう。
| 活動内容 | 手続き例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 路上ライブのみ | 管理団体申請 | 地域の条例も確認 |
| 投げ銭あり | 追加で許可・申請要 | 収益化は要注意 |
| CD販売 | 複製許可が必要 | 権利者の確認が必須 |
市販楽譜や音源の使用制限と合法利用のポイント
市販されている楽譜や音源を使って演奏する場合にも、著作権の観点から注意が必要です。楽譜や音源には、作詞・作曲の権利だけでなく、出版社やレコード会社の権利も関わることがあります。
たとえば、市販楽譜をコピーして配布したり、市販CDをそのまま流したりすることは、著作権法で制限されています。合法的に利用するには、必ず正規品を購入し、私的利用の範囲を超えて使用したい場合は関係者に許可を取る必要があります。また、演奏を録音して配布する場合も「複製権」「公衆送信権」などの権利が関わるため、事前確認をして安心して利用しましょう。
カバー曲の制作販売と音楽活動で知っておきたい権利関係
カバー曲を制作したり、CDや配信で販売する場合には、さらに多くの権利が関わってきます。活動の幅を広げる前に知っておきたいポイントをまとめました。
デジタル配信やCD販売に必要な権利処理
カバー曲をCDで販売したり、配信サービスでリリースする場合には「複製権」と「頒布権」の許可が必要です。これらは楽曲の原作者や権利管理団体が持つ権利で、正規の手続きを取らないと著作権侵害となる可能性があります。
国内配信の場合、JASRACやNexToneを通じて「原盤許諾」や「配信許諾」の申請ができます。海外配信の場合は、別途海外の著作権管理団体とやりとりが必要な場合もあります。手続きの詳細は各管理団体のウェブサイトや、配信サービスのガイドラインを参考にするとよいでしょう。
歌ってみた動画やアレンジ作品の著作権
「歌ってみた」動画や、自分なりにアレンジした楽曲を公開する場合も、原曲の著作権が関わります。たとえば、ボーカルだけを入れ替えても、元の作詞・作曲者の権利は残ったままです。
また、大きくアレンジした場合は「翻案権」という権利が関わり、原作権利者の許可が必要になることがあります。YouTubeなどで公開する場合は、JASRACやNexToneとの契約の範囲内で許可されているか確認し、必要ならば追加の申請も検討しましょう。
申し立てやトラブル時の対処方法と相談先
カバー曲の配信や販売で著作権の申し立てやトラブルが発生した場合は、まず冷静に状況を確認しましょう。動画プラットフォームからの連絡があれば、どの権利が問題になっているかを詳細に確認することが大切です。
対応策としては、著作権管理団体(JASRACやNexTone)への相談や、音楽関係の法律相談窓口を利用する方法があります。自分で解決が難しい場合は、専門の知識を持つ弁護士や相談機関にアドバイスを求めることも有効です。早めの対応がトラブル解決のポイントとなります。
まとめ:カバー曲と著作権を正しく理解し安心して音楽活動を楽しもう
カバー曲の演奏や配信には、さまざまな著作権上のルールと手続きがあります。必要な知識を身につけ、正しく手続きを行うことで、安心して音楽活動を楽しむことができます。
著作権管理団体や各種ガイドラインを確認し、疑問点があれば早めに相談窓口を活用しましょう。ルールを守って音楽活動を進めることで、自分の表現をより自由に広げることができます。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!