ドラムフラムとは何か基本を知ろう
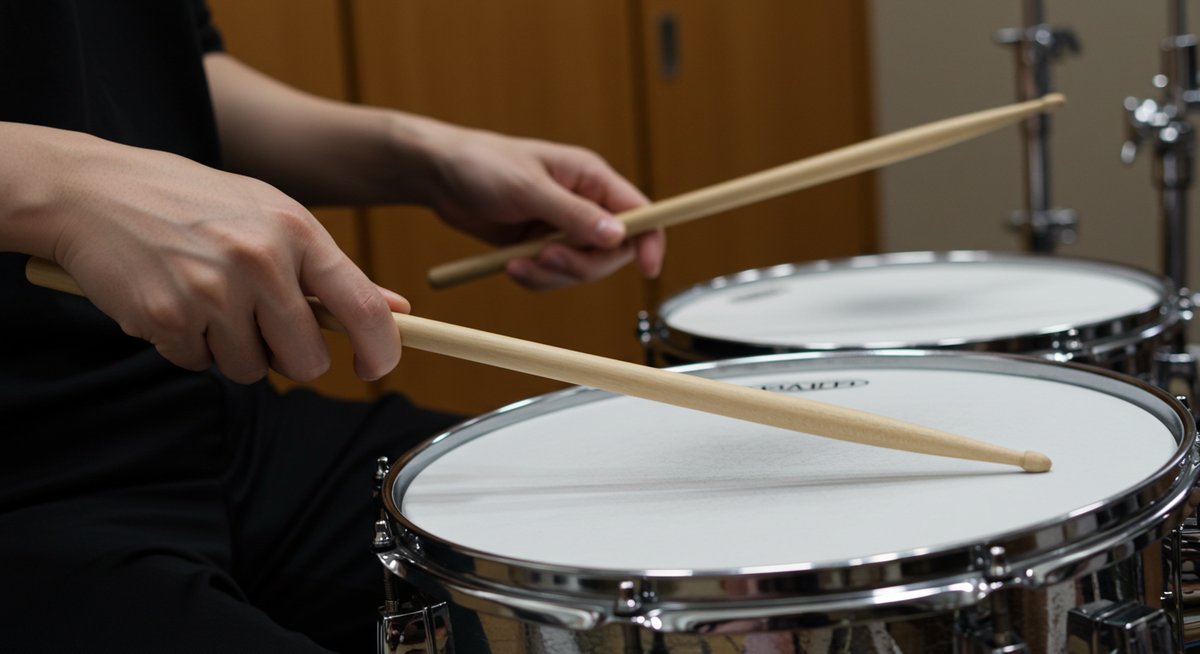
ドラムフラムは、叩き方に独自のニュアンスが生まれる重要なテクニックです。まずは意味や特徴を知って、表現の幅を広げてみましょう。
フラムの意味と役割
フラムとは、ドラムで2本のスティックを使い、わずかにタイミングをずらして連続してたたく奏法を指します。このとき、主に先に「おとり」として軽くたたく音と、そのあとに続けてメインの音をたたく形になります。両方の音を同時に鳴らすのではなく、ほんの少し時間差をつけて鳴らすのが特徴です。
フラムを使うことで、普通に一打だけでたたくよりも音に厚みやアクセントが加わり、リズムに個性を持たせることができます。曲の中で要所にフラムを取り入れると、流れに変化を与えられるため、演奏の表現力が向上します。また、マーチングバンドやロック、ポップスなど様々な音楽ジャンルで活用される基本テクニックとなっています。
フラムの譜面での表記方法
フラムはドラム譜面で特有の記号を使って表されます。一般的には、メインの音符の前に小さな音符(グレースノート)が付いている形で書かれています。この小さい音符は、おとりの音を意味していて、メインの音の直前に置かれます。
実際の譜面では次のように表されます。
| メインの音 | おとりの音(グレースノート) |
|---|---|
| 通常の大きさの音符 | 小さい音符 |
このような表記を見ることで、どこにフラムが入るのかを判断しやすくなります。最初は譜面上の違いに戸惑うかもしれませんが、見慣れればすぐに理解できるようになります。
他のルーディメンツとの違い
ルーディメンツとは、ドラム演奏の基本パターンをまとめた用語で、フラムもその1つです。ほかにもパラディドルやドラッグといった種類がありますが、フラムは単純に2つの音を短い間隔で打つ点が違いといえます。
一例を挙げると、パラディドルは「左右交互に打つ動き」と「ダブルストローク(二度打ち)」が組み合わされているのに対して、フラムは左右どちらかの手でおとりの音をたたき、もう一方の手で本命の音をたたくというシンプルな構造です。そのため、他のルーディメンツに比べて感覚的に覚えやすい反面、音の粒をそろえることやリズムの精度が求められます。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!
フラムの叩き方と練習のコツ

フラムを上手く演奏するためには、打ち方や手の動かし方に意識を向けて練習することが大切です。ここからは、具体的なコツや注意点をご紹介します。
正しいスティックコントロール
フラムをきれいにたたくためには、両手のスティックの高さの違いと動かし方を意識することが重要です。おとりの音は低く控えめに、メインの音は高く強めに振り下ろします。この高さの差をしっかりつけることで、音の粒立ちが良くなり、フラムらしいサウンドが生まれます。
また、手首の柔らかさと指先のリラックスも大事です。力みすぎずにスティックを握り、速い動きでも無駄な力が入らないようにしましょう。最初はゆっくりとしたテンポで、動きを確認しながら練習すると正しいフォームが身につきやすいです。
音の間隔と強弱を意識する方法
フラムは2つの音の間隔(タイミング)がポイントです。おとりの音とメインの音が近すぎると単なる一打になってしまい、逆に離れすぎると別々の音に聞こえてしまいます。理想は、2つの音が「タタッ」と聞こえるくらいの間隔で打つことです。
音量にも注意しましょう。おとりの音は控えめにし、メインの音ははっきりと発音します。もし音のバランスやタイミングがそろわない場合は、片手だけでそれぞれの動きを反復したり、録音して自分の音を確認してみるのも効果的です。地道な繰り返しで、きれいなフラムに近づけます。
初心者が陥りやすい失敗パターン
フラムの練習で初心者がよくつまずくポイントがあります。たとえば、両手で打つタイミングがずれてしまい、2つの音が離れすぎたり、逆に同時に鳴ってしまうことが挙げられます。
また、両方の音が同じ強さになってしまうこともよくあるミスです。おとりの音が大きすぎると、フラム独特のニュアンスが出ません。さらに、スティックを握る力が強すぎて動きが硬くなり、速いフレーズが難しく感じることもあるでしょう。失敗しやすいポイントを自覚し、少しずつ丁寧に修正していくことが大切です。
フラムを使った練習フレーズと応用例

フラムは単独で使うだけでなく、さまざまなフレーズや応用テクニックにも発展します。代表的なパターンやバンド演奏での使いどころを見ていきましょう。
フラムタップとフラムアクセントの違い
フラムタップとフラムアクセントは、どちらもフラムを発展させたパターンですが、それぞれ特徴が異なります。フラムタップはフラムのあとにタップ(軽い一打)を連続で加える奏法で、滑らかな流れを生みます。フラムアクセントは、フラムを使ってアクセント(強調)を加えたリズムパターンで、楽曲の中でリズムをくっきりと際立たせたいときに用いられます。
| パターン名 | 特徴 | 使用例 |
|---|---|---|
| フラムタップ | フラム+連続タップ | ロールの中やフィルイン |
| フラムアクセント | フラム+アクセント | リズムの強調・装飾 |
どちらも慣れれば様々な音楽ジャンルで自由に取り入れることができ、演奏表現の幅が広がります。
フラムパラディドルやスイスアーミートリプレットの練習
フラムパラディドルは、パラディドル(左右交互+ダブルストローク)にフラムを加えたパターンです。一方、スイスアーミートリプレットはトリプレット(3連符)の中にフラムを組み込んだ特殊な形です。これらは少し難易度が上がりますが、練習することで複雑なリズムや装飾的なフレーズを演奏できるようになります。
最初はゆっくりしたテンポで、両手の動きやフラムの位置を丁寧に確認しましょう。慣れてきたら徐々にテンポを上げていくのがおすすめです。難しいと感じる場合は、1パターンを数小節ずつ区切って繰り返し練習することで無理なく上達できます。
バンドや曲でフラムを使うポイント
バンド演奏や曲の中でフラムを使う場面は多く、特にドラムフィルや印象的な入りなどで効果を発揮します。たとえば、曲の盛り上がりやサビ前のフレーズに取り入れることで、リズムにアクセントがつき、全体にメリハリが生まれるでしょう。
また、フラムはスネアドラムだけでなく、タムやバスドラムと組み合わせることでも独特の響きを作り出せます。自分の好きな楽曲を分析して、どこにフラムが使われているかを探してみるのも、応用のヒントになります。
フラム上達のためのおすすめ練習法

フラムがきれいに叩けるようになるには、毎日の基礎練習と工夫したトレーニングが重要です。具体的な練習法やコツを紹介します。
基本パターンを繰り返すトレーニング
まずは左右それぞれ、フラムを交互に打つ基本練習を繰り返しましょう。右フラム・左フラムを決まった数ずつ交互に行い、音の粒や間隔がそろうよう意識します。
短い時間でもよいので、毎日続けることで自然と安定したフォームやタイミングが身につきます。下記のようなシンプルなパターンを使い、ゆっくりと始めて徐々にスピードアップしていくと効果的です。
| パターン | 説明 |
|---|---|
| 右フラム | 右手メインでフラム |
| 左フラム | 左手メインでフラム |
| 交互 | 右・左交互でフラム |
メトロノームを活用したリズム強化
リズム感を鍛えるためには、メトロノームを使った練習が有効です。一定のテンポに合わせてフラムを打つことで、タイミングのズレや音の間隔を正確に保つことができます。
練習方法としては、最初は60~80のゆったりしたテンポに設定し、フラムを1拍ごとに打ってみましょう。慣れてきたらテンポを上げていくことで、速いフレーズにも対応できるようになります。リズムの精度が上がることで、バンド演奏でも安心してフラムを取り入れられるようになります。
フラムを活かすための身体の使い方
フラムをきれいに演奏するには、無駄な力を抜いて効率よく身体を使うことが大切です。肩や腕が力んでしまうと動きがぎこちなくなり、音のバラつきやスピード不足につながります。
意識したいポイントは、手首と指先を中心に動かすことと、スティックの跳ね返りをうまく活用することです。また、練習の前後に軽いストレッチを取り入れて、疲れやすい部位をケアするのもおすすめです。無理のない姿勢を心がけることで、長く楽しく練習を続けられます。
まとめ:ドラムフラムを身につけて幅広い表現力を手に入れよう
ドラムフラムは、叩き方や練習法を工夫することで誰でも上達できるテクニックです。基礎を大切にしながら、徐々に応用パターンも取り入れていきましょう。
身につけることで、バンド演奏や楽曲の中でリズムやアクセントに多彩な表現を加えられるようになります。毎日の小さな積み重ねが大きな上達につながるので、焦らず楽しみながら練習を続けてみてください。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!










