純正律とは何か理解しやすく解説
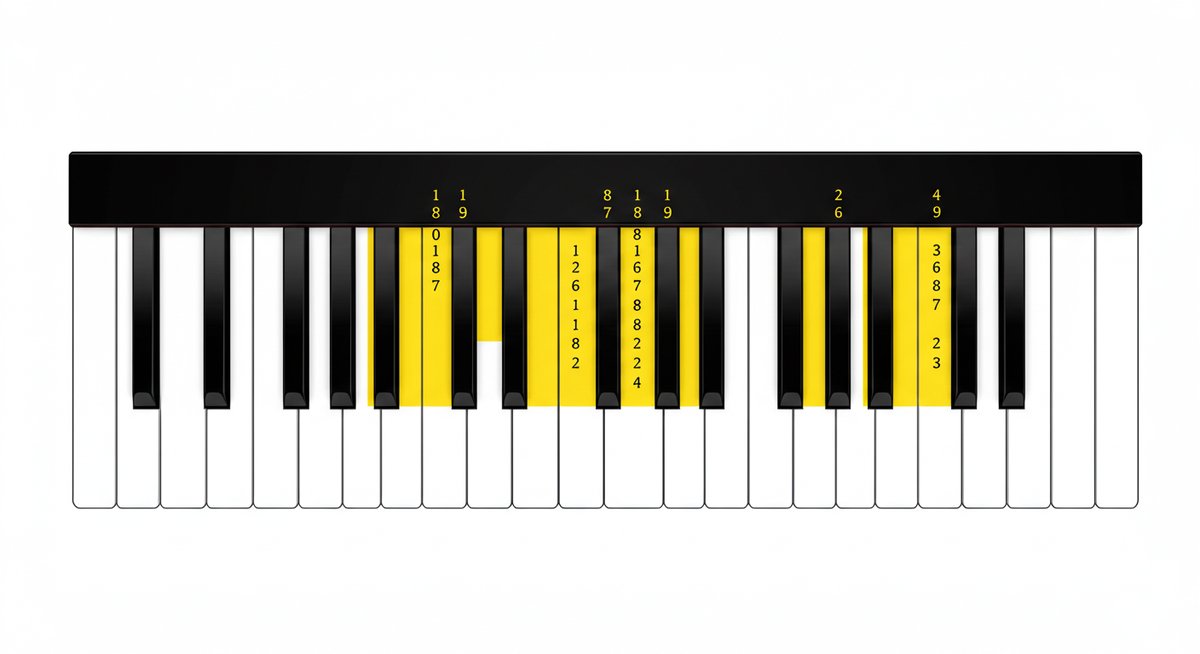
純正律は音楽の中でも特に美しい響きを生み出す調律法の一つです。身近な音楽や楽器にも関わりが深い純正律について、仕組みや特徴を分かりやすく紹介します。
純正律の基本的な仕組み
純正律は、複数の音が同時に鳴ったときの響きが自然で心地よく感じられるように、音と音の関係(音程)を整数比で整える調律法です。たとえば、ドとソという音の間を3:2という簡単な比率に合わせることで、二つの音が調和しやすくなります。
この整数比による調律は、古代から伝えられてきた音楽理論の一つです。一般的に「ド・ミ・ソ」といった和音を作ったとき、濁りの少ない透明感のある響きが得られるのが特徴です。ただし、純正律で調律した楽器は、すべての調(キー)で同じ質の和音を保つのが難しく、調ごとに音の高さを変える必要が出てきます。
純正律と平均律やピタゴラス音律との違い
純正律とよく比べられるのが、平均律とピタゴラス音律です。それぞれの違いは主に「音程の取り方」にあります。純正律は整数比を重視し、和音の響きが美しくなるように調律されます。一方、平均律は12の半音をすべて等しい幅に分けているため、どの調でも同じ感覚で演奏できますが、純正律ほどの澄んだ和音にはなりません。
ピタゴラス音律は、主に5度の音程(例:ドからソ)を基準として音を積み上げていく調律法です。ピタゴラス音律は旋律を演奏するには向いていますが、和音を鳴らすと純正律ほどの調和は感じられない場合もあります。純正律は和音、平均律は移調やさまざまな調への対応、ピタゴラス音律は旋律での美しさにそれぞれ強みがあります。
純正律が使われる音楽ジャンルや楽器
純正律は、主に古楽や宗教音楽、ア・カペラ合唱などで広く使われてきました。ピアノやギターのような多くの調にすぐ移れる楽器では平均律が一般的になりましたが、固定された和音が中心になるジャンルでは今でも純正律の美しい響きが好まれています。
たとえば、以下のようなジャンルや楽器で純正律が用いられることがあります。
- ア・カペラ合唱(人の声で微調整できるため)
- ルネサンスやバロック時代の鍵盤楽器
- 宗教音楽や伝統音楽
- 特殊な調律が可能な弦楽器(ヴァイオリン属など)
また、最近では電子楽器や音楽ソフトを使った現代音楽の制作でも、純正律を取り入れる流れが広がっています。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!
純正律の周波数の決まり方と計算方法

純正律の音程は、単純な数字の比率で決まるため、周波数の計算も比較的分かりやすい特徴があります。その仕組みや例を紹介します。
純正律における周波数比の特徴
純正律では、音と音の間隔(音程)を2つの整数の比で表します。代表的な周波数比は次の通りです。
- 2:1(オクターブ)
- 3:2(完全五度)
- 5:4(長三度)
このように、基本的な和音が単純な数字の比率になることで、倍音成分がきれいに重なり、響きが安定します。純正律の調律は、主音を決めてからそれぞれの比率を掛けて周波数を導き出すのが一般的です。
整数の比が複雑になると響きが濁りやすくなるため、純正律ではできるだけ簡単な比率を使い、和音の透明感を高める工夫がなされています。
主な音程ごとの周波数計算例
実際に純正律で周波数を求める方法を簡単な例で紹介します。たとえば、基準のドの音を440Hzとした場合、それぞれの音は次のように計算します。
| 音程 | 周波数比 | 計算方法 |
|---|---|---|
| オクターブ | 2:1 | 440Hz × 2 = 880Hz |
| 完全五度 | 3:2 | 440Hz × 3 ÷ 2 = 660Hz |
| 長三度 | 5:4 | 440Hz × 5 ÷ 4 = 550Hz |
このように、比率を掛け算や割り算に当てはめることで、ドレミファソラシド各音の周波数を決めていきます。純正律では、調を変える(別の主音にする)と、同じ名前の音でも周波数が変わる点も特徴です。
純正律の周波数比が生む響きの美しさ
純正律の大きな魅力は、単純な周波数比によって生まれる自然な響きです。複数の音が重なったとき、波の山や谷がきれいに揃いやすく、濁りが少ない透明感のある和音になります。
とくに合唱や弦楽アンサンブルなどでは、演奏者同士が耳で調整しながら純正律に近づけることができるため、うっとりするような響きが生まれやすいです。反対に、平均律よりも複雑な調への移調には向きませんが、特定の調でのハーモニーの美しさを大切にしたいときに純正律は力を発揮します。
純正律を活かすための楽器選びと調律の工夫

純正律の響きを最大限に生かすには、楽器の種類や調律法にも工夫が必要です。どんな楽器が適しているのか、調律の特徴やポイントを解説します。
純正律に適した楽器の種類と特徴
純正律で調律しやすい楽器には、音の高さを細かく調整できるものが多いです。主な例は以下の通りです。
- 弦楽器(バイオリン、チェロなど)
- 管楽器(声帯や息で音程調整可能なもの)
- 声楽(合唱や独唱)
これらの楽器や声は、演奏のたびに微妙に音程を動かせるため、純正律でハーモニーを合わせやすい特徴があります。一方、ピアノやギターなどは一度調律すると音程が固定されるため、純正律での演奏には制約があります。
近年では電子楽器やシンセサイザーでも細かな音程設定ができる機種が増えており、純正律を取り入れた新しい音楽表現も試みられています。
純正律での調律方法とその難しさ
純正律の調律は、主音を決めてから周波数比をもとに各音を合わせる方法が一般的です。しかし、すべての調で純粋な和音を得るのは難しいという側面もあります。
たとえば、ピアノのような鍵盤楽器では、一つの調で純正律に調律すると、転調(ほかの調への移動)をしたときに和音が濁りやすくなります。そのため、合唱や弦楽器のアンサンブルのように、演奏中に音程を微調整できる場面で純正律はより活用しやすいです。調律の際は、基準の音を決めて各音の周波数比を守ることが大切になります。
純正律を用いた演奏で意識すべきポイント
純正律で演奏する際は、耳を使った微調整が重要です。とくに複数人で演奏する場合、互いの音をよく聴きながら、和音がもっとも澄んで聞こえるポイントを探します。
具体的には、次のような点を意識すると良いでしょう。
- 各パートが主音やベース音を基準に音程を合わせる
- 和音の響きに濁りやうねりがないか確認する
- 必要に応じてその場で音程を微調整する
このような工夫を重ねることで、純正律ならではの美しいハーモニーが生まれます。
純正律と現代音楽の関係や応用事例

純正律は古くからある調律法ですが、現代音楽の中でも新しい活用法が注目されています。その歴史や応用事例、今後の可能性を見ていきます。
クラシック音楽と純正律の歴史的な関係
クラシック音楽の初期、とくにルネサンスやバロック時代には、純正律が和声の響きを重んじる音楽制作に広く使われていました。合唱や宗教曲では、純正律による和音の美しさが重視され、作曲家たちもこの響きを意識して作品を作っていました。
しかし、時代が進むにつれ、さまざまな調への転調が求められるようになり、純正律だけでは対応できない場面が増えていきました。そのため、現在の一般的なクラシック音楽では平均律が多く使われていますが、純正律の響きを再現しようとする試みは今も続いています。
現代音楽制作での純正律の導入例
現代音楽やポップスの制作現場では、パソコンや電子楽器の普及により、純正律の音程を簡単に設定できるようになりました。たとえば、DTM(パソコンでの音楽制作)ソフトやシンセサイザーでは、平均律だけでなく純正律も選択可能です。
また、映像音楽やアンビエント音楽などで、美しい響きを強調したい場面で純正律が用いられることがあります。独特のハーモニーや澄んだ和音を生かした新しい楽曲も生まれています。
純正律による音楽表現の可能性と今後の展望
純正律は、和音の透明感や独自の響きを表現できるため、今後ますます注目される要素です。特に、AIや最新の音楽ソフトを活用することで、複雑な調律も容易になり、多彩な音楽スタイルに取り入れやすくなっています。
今後は、従来のジャンルにとどまらず、映画音楽や現代アート音楽、教育現場などさまざまな分野での応用が期待されています。純正律の魅力を知ることで、音楽の新たな楽しみ方や表現方法がさらに広がるでしょう。
まとめ:純正律と周波数が音楽にもたらす魅力と実践のポイント
純正律は、シンプルな周波数比による調和のとれた響きが最大の魅力です。和音の美しさや心地よさを追求する際にとても役立ちます。
純正律を活かすには、適した楽器や調律法、演奏時の耳による微調整が大切です。現代では電子楽器や音楽制作ソフトの発展により、純正律を気軽に取り入れる環境も整ってきています。ぜひ純正律の特性を知り、日々の音楽体験や演奏に役立ててみてください。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!










