作詞と作曲はどっちが先か初心者が知っておくべき考え方

曲作りを始めたい方がまず悩むのが、「作詞」と「作曲」のどちらから始めればよいかという点です。自分に合った方法を見つけるための基本的な考え方を解説します。
作詞と作曲それぞれの特徴と役割
作詞は楽曲の言葉やテーマを決める作業で、何を伝えたいのか、どんなストーリーにするのかを考えます。一方で作曲はメロディやコード進行を作り、曲全体の雰囲気や印象を左右します。
どちらも曲作りに欠かせない要素ですが、誰かに「どちらが大事か」と聞かれても一概に答えるのは難しいところです。人によってアイデアが言葉から湧くこともあれば、メロディから生まれることもあるためです。自分自身が楽しいと感じる方から始めるのが続けやすい方法といえるでしょう。
作詞先と作曲先それぞれのメリット
作詞を先にする「詞先」は、伝えたい内容やメッセージをしっかりと決めてから曲作りに入れる点が強みです。一方、作曲を先にする「曲先」は、感覚的に浮かんだメロディやリズムをそのまま活かせるので、音楽的な自由度が高くなります。
それぞれのメリットを整理すると、以下のようになります。
| 作り方 | メリット | おすすめの人 |
|---|---|---|
| 詞先 | 世界観を重視しやすい | 歌詞で表現したいテーマが明確な人 |
| 曲先 | メロディを自由に作れる | 旋律やリズムが浮かびやすい人 |
自分がどちらのやり方に興味を持てるか、一度試してみるのも良い方法です。
作詞作曲の順番で変わる曲作りのアプローチ
作詞先の場合は、できあがった歌詞に合うメロディやコードを考えるため、言葉に合わせて曲の雰囲気を細かく調整できます。また、感情や情景を歌詞から受け取って表現できるのも特徴です。
一方、作曲先の場合は、先に作ったメロディに合う言葉やテーマを考えるため、自然と口ずさみたくなるような曲を作りやすくなります。ただし、言葉がメロディに縛られる場合があるため、柔軟な発想が求められます。順番によって曲作りのアプローチが大きく変わるため、自分に合った方法を模索してみましょう。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!
作詞が先の場合に意識したいポイント

作詞から始める場合、歌詞の内容や表現が曲の印象を決める大きな要素となります。より良い楽曲にするための重要なポイントを整理します。
歌詞のテーマや世界観の決め方
作詞を始める際は、まずどのようなテーマや世界観で書きたいかを考えることが大切です。たとえば「青春」「別れ」「夢」など、大まかな軸を決めておくと、歌詞全体に統一感を持たせやすくなります。
また、自分の体験や感じたことをベースにすると言葉選びにも説得力が生まれます。イメージをふくらませるために、思い浮かぶ情景やキーワードをメモしておくのも効果的です。歌詞作りで迷った時は、実際に他の曲の歌詞を参考にしてみても良いでしょう。
メロディに合わせやすい歌詞の書き方
詞先の場合でも、後でメロディをつけやすい歌詞にしておくことが望ましいです。たとえば、あまりに複雑な言い回しや長すぎる文章はメロディと合わせづらくなるので、簡潔でリズミカルな表現を意識しましょう。
箇条書きでポイントを整理すると次の通りです。
- 1行の文字数を揃える
- 音の響きを意識する(たとえば母音や繰り返し)
- サビや繰り返しに使いやすい言葉を用意する
このような工夫をすることで、後から曲をつける際にも自然な流れに仕上がります。
詞先で起こりやすい失敗例とその対策
詞先でよくある失敗の一つが、言葉に思い入れが強すぎてメロディに合わせる部分が窮屈になってしまうことです。また、内容を詰め込みすぎて歌いにくくなるケースもよく見られます。
このような場合は、余分な言葉を削ったり、1行の長さを調整することでバランスをとることが解決につながります。どうしても直しきれない場合は、部分的に言葉を置き換えるなど柔軟に対応すると良いでしょう。
作曲が先の場合のコツと注意点
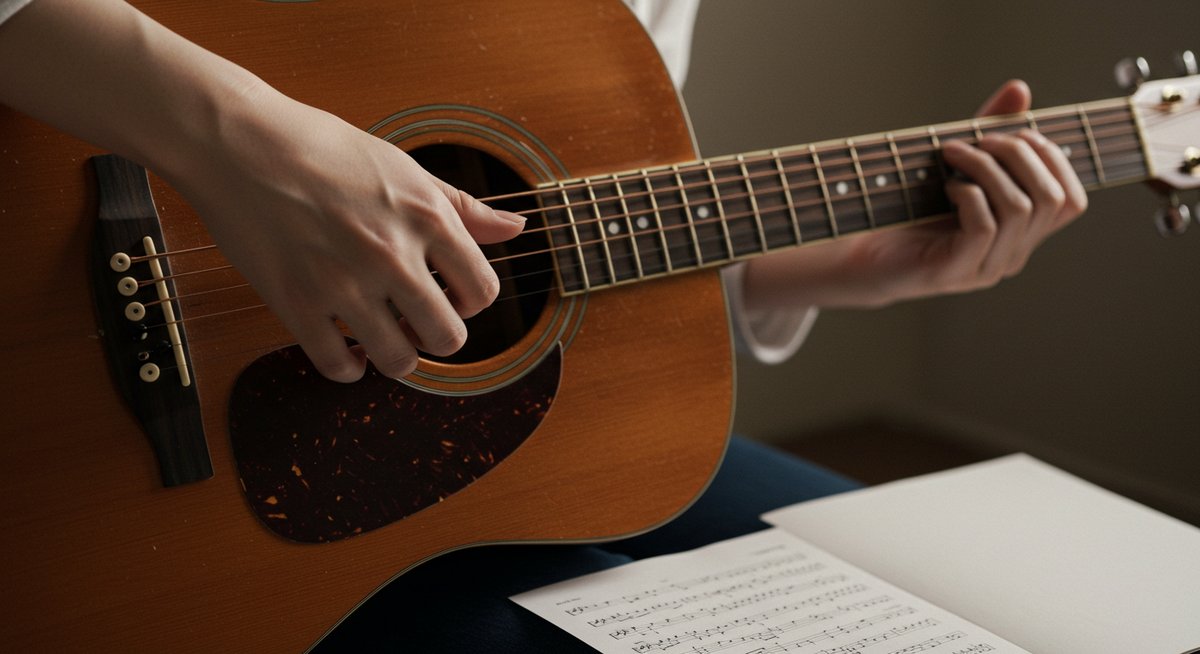
作曲から始める場合は、メロディやリズムにしっかりとした個性を持たせつつ、歌詞とのバランスも意識することがポイントになります。
メロディから生まれる曲作りの流れ
作曲先では、まずピアノやギターなどでメロディのアイデアを出すことから始まります。浮かんだフレーズを録音しておくと、後から見直して発展させるのに役立ちます。
複数のメロディを用意して、その中から一番しっくりくるものを選ぶのも有効です。最初はシンプルな構成から始め、徐々にアレンジを加えていくことで楽曲の完成度が高まります。
曲のイメージに合う歌詞をつける方法
できあがったメロディに歌詞をつける際は、曲の雰囲気やリズムに合わせた言葉選びが大切です。たとえば明るいメロディならポジティブな言葉を、しっとりした曲調なら感情を重視した表現が合います。
また、以下のようなポイントを意識すると、曲と歌詞が自然にマッチしやすくなります。
- 曲の拍やリズムに言葉を合わせる
- 強調したい部分に印象的なフレーズを入れる
- メロディの高低に合わせて感情を表現する
このように、音と歌詞がお互いを引き立て合う工夫が重要です。
曲先でよくある悩みと解決策
曲先の場合、「メロディに合う言葉がなかなか見つからない」と悩むことがあります。また、歌詞を後付けにすると、言葉が不自然に感じることもあるでしょう。
そのようなときは、無理にひとつの単語にこだわらず、意味が近い言葉をいくつか並べてみて響きを比べてみると、新しい発見があります。また、歌詞の一部を英語や意味のないフレーズにすることで、メロディを壊さずに自然な流れを作れる場合もあります。
ハイブリッドな作詞作曲や他の方法も紹介

作詞と作曲の順番に正解はなく、同時進行や他のアプローチで曲作りをする方法もあります。柔軟にアイデアを活かす工夫を見ていきましょう。
同時進行で作詞作曲を行うコツ
作詞と作曲を同時に進める場合は、簡単な言葉やフレーズを口ずさみながらメロディを作る方法が一般的です。言葉と音のバランスをその場で調整できるため、自然な一体感が生まれやすくなります。
また、短いサビやリフレインの部分だけ先に決めてしまい、そこを軸にして全体を組み立てる方法も効果的です。このやり方は、自由な発想で曲作りを進めたい人にとくにおすすめです。
コード進行やトラックから曲を作る方法
近年はピアノやギターのコード進行、さらにパソコンで作る「トラック」から曲全体を発想する方法も広がっています。まず、好きなコード進行やトラックを作り、その雰囲気に合うメロディや歌詞を後から重ねていきます。
このアプローチは、バンドだけでなくDTM(パソコンを使った音楽制作)をする人にも向いています。音のイメージを先に固めることで、曲全体の方向性が定まりやすくなる点が特徴です。
バンドやユニットでの役割分担と進め方
バンドやユニットで曲作りをする場合は、それぞれの得意分野を活かして役割を分担することが大切です。たとえば、歌詞が得意な人が作詞を、楽器が得意な人が作曲を担当することで、効率的に制作を進められます。
また、全員でアイデアを出し合いながら進めることで、思わぬ発想や新しい展開が生まれることもあります。バンド内で意見がぶつかったときは、いったん別のアイデアを試してみるなど柔軟な対応を心がけましょう。
まとめ:自分に合った作詞作曲の順番を見つけよう
作詞と作曲の順番や方法にはさまざまなパターンがあり、正解は一つではありません。自分の得意なやり方や、曲ごとのテーマに合わせた方法を試してみることが大切です。
気軽にいろいろなアプローチを取り入れながら、音楽作りを楽しんでください。続けていくうちに、きっと自分らしい曲作りのスタイルが見えてくるはずです。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!










