サスフォーとは音楽理論でどのようなコードか
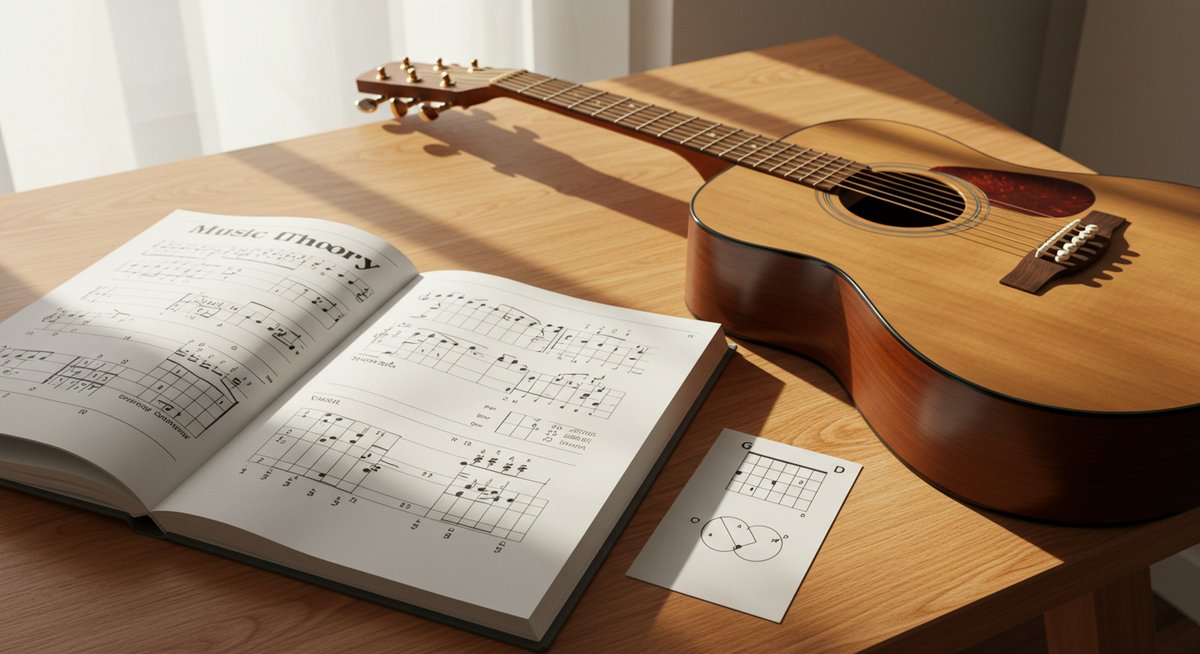
サスフォーは、楽曲に独特の響きを加えるコードとして、多くのジャンルで使われています。初心者から上級者まで幅広い演奏者に親しまれています。
サスフォーコードの構成音と特徴
サスフォーコードは、基本的な三和音の中で三度の音を四度の音に置き換えたコードです。たとえば、Cコードの場合、通常はC(ド)、E(ミ)、G(ソ)という音で構成されていますが、サスフォーになるとE(ミ)がF(ファ)に変わり、C(ド)、F(ファ)、G(ソ)となります。
このように四度の音を加えることで、独特の浮遊感や緊張感のある響きが生まれます。サスフォーは「suspended 4th(サスペンデッド・フォース)」の略で、直訳すると「四度がぶらさがっている」という意味です。元々の三度の和音とは違い、不安定な印象を持ちますが、それが次のコードへの期待感を作り出します。
サスフォーが生まれた背景と由来
サスフォーコードは、クラシック音楽の時代から「解決を待つ音」として使われてきました。特に和声の流れの中で、不安定な響きを作り出し、次に進むきっかけを与える役割を果たしています。
現代のポピュラー音楽やロック、ジャズなどでも広く使われるようになり、楽曲に緊張と解放のコントラストを加えるために活用されています。また、ギターやピアノを使うバンド演奏で頻繁に登場することから、バンドサウンドの表現力を高める要素としても定番となっています。
メジャーコードやマイナーコードとの違い
メジャーコードは明るい響き、マイナーコードはやや暗い響きを持ちますが、サスフォーコードはそのどちらとも異なる印象を与えます。三度の音が無くなることで、メジャー・マイナーの区別がつきにくくなり、中立的で曖昧な響きを作り出します。
また、サスフォーは基本的に一時的なコードとして使われることが多く、その後に解決する流れが一般的です。特に、次にメジャーやマイナーのコードが来ることで、より一層その効果が際立ちます。下の表は、メジャー、マイナー、サスフォーの構成音の違いをまとめています。
| コード種類 | 構成音例(Cの場合) | 響きの特徴 |
|---|---|---|
| メジャー | C・E・G | 明るい |
| マイナー | C・E♭・G | やや暗い |
| サスフォー | C・F・G | 浮遊感・緊張感 |
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!
サスフォーコードの使い方と効果的な活用例

サスフォーコードは、さまざまな場面で効果的に使われます。ここでは、よく用いられる使い方や活用例について詳しく解説します。
ドミナントコードでのサスフォーの利用
ドミナントコード(主にVの和音)は、楽曲の中で「次に進みたい」と感じさせる役割を持っています。ここでサスフォーコードを使うと、より強い期待感や盛り上がりを演出することができます。たとえば、G7(ソ・シ・レ・ファ)の代わりにGsus4(ソ・ド・レ・ファ)を入れると、一時的に緊張が高まり、その後の解決が際立ちます。
特にバンドや合唱では、このサスフォーから通常のドミナントコードに戻る動きが印象的に響きます。リスナーに「次にどうなるのか」と感じさせることで、楽曲全体の表現力を高める効果が期待できます。
トニックやサブドミナントでのサスフォーの活用
トニック(Iの和音)やサブドミナント(IVの和音)でもサスフォーコードは使われます。たとえば、Cコードの代わりにCsus4を使い、一時的な変化や色彩を加えることができます。サブドミナントでは、コード進行に柔らかな変化をつけたり、フレーズのつなぎ目で雰囲気を変えるのに役立ちます。
また、バラードやポップスのイントロやアウトロ部分でサスフォーを取り入れることで、楽曲に奥行きを出すことができます。特にピアノやアコースティックギターのアレンジでは、サスフォーを効果的に使う場面が多く見られます。
サスフォーコードを使った有名楽曲の例
サスフォーコードは多くの有名曲に取り入れられています。たとえば、ビートルズの「Let It Be」やボブ・ディランの「Knockin’ on Heaven’s Door」などは、印象的なコード進行の中にサスフォーが登場します。
また、日本のポップスやアニメソングでも印象的な場面で多用されています。イントロやサビの直前でサスフォーを入れることで、楽曲に特徴的なアクセントを加えています。こうした実例を参考にすると、自分の作曲や演奏にも取り入れやすくなるでしょう。
サスフォーコードのバリエーションと応用テクニック

サスフォーコードにはさまざまな派生形や応用方法があります。ここでは、実際のバンド演奏や作曲で役立つテクニックについて解説します。
セブンスコードへのサスフォーの追加
セブンスコードにサスフォーの音を加えることで、さらに豊かな響きが生まれます。たとえば、G7sus4はG、C、D、Fという構成になります。原則として、通常のセブンスコードの三度の音を四度に置き換え、セブンスの音(この場合はF)を加えます。
このようなコードはブルースやポップス、R&Bなど幅広いジャンルでよく使われています。セブンスの持つ「締める」役割とサスフォーの「ぶらさがる」響きが合わさることで、コード進行に彩りをもたらします。
マイナーコードでのサスフォーの応用
マイナーコードにもサスフォー的なアプローチが可能です。たとえば、Am(ラ・ド・ミ)の三度(ド)を四度(レ)に置き換えてAmsus4(ラ・レ・ミ)とすることで、通常のマイナーコードにはない雰囲気を演出できます。
この応用は切なさを強調したいときや、コード進行の途中で一時的な緊張感を加えたい場面で使われます。マイナーサスフォーは、フォークやロックのバラードなど、情感を大切にしたい楽曲で特に効果的です。
サスフォーとサスツーの違いと使い分け
サスフォーとよく比較されるのがサスツー(sus2)です。サスツーは三度の音を二度の音に置き換えたコードで、サスフォーよりもやわらかく開放的な響きになります。
| コード名 | 構成音(Cの場合) | 響きの特徴 |
|---|---|---|
| Csus4 | C・F・G | 緊張感・浮遊感 |
| Csus2 | C・D・G | やわらかさ |
使い分けのポイントとしては、曲により強い緊張感や期待感を出したい場合はサスフォーを、穏やかに広がる雰囲気を出したい場合はサスツーを選ぶと良いでしょう。
サスフォーコードを楽器で演奏するコツ

サスフォーコードはギターやピアノなど、さまざまな楽器で演奏できます。ここでは、演奏時に役立つポイントやコツを紹介します。
ギターでのサスフォーコードの押さえ方
ギターでは、サスフォーコードは比較的簡単な指使いで押さえることができます。たとえば、Cコードの場合、通常のフォームで2弦1フレットを2フレットに移動させるだけでCsus4になります。
また、Gsus4やDsus4なども、基本コードから指一本の移動で押さえることが可能です。サスフォーコードを使うことで、ストロークやアルペジオにバリエーションが加わり、アレンジの幅が広がります。練習の際は、定番のコード進行の中にサスフォーを取り入れ、音の変化を実感してみると良いでしょう。
ピアノでサスフォーコードを弾くポイント
ピアノでサスフォーコードを弾く場合、三度の音を弾かずに、その代わり四度の音を加えます。たとえば、C(ド)、F(ファ)、G(ソ)という形で鍵盤に手を置きます。
また、コード進行の中でサスフォーを入れると、伴奏にアクセントや変化を付けやすくなります。右手の和音だけでなく、左手のベース音を合わせて演奏することで、より厚みのあるサウンドが生まれます。反復練習を通じて、指の動きと音の響きを体で覚えることが大切です。
コード進行にサスフォーを取り入れる方法
サスフォーコードをコード進行に取り入れる際は、主要なコード(I、IV、Vなど)の間や、フレーズの切れ目で使うと効果的です。たとえば、「C→Csus4→C」といったように、同じコードの中でサスフォーを挟むことで自然な動きが生まれます。
また、「G→Gsus4→G→C」など、ドミナントからトニックに進む直前でサスフォーを入れると、曲にメリハリがつきます。下記は簡単なコード進行例です。
- C→Csus4→C→F
- G→Gsus4→G→C
こうしたパターンをいくつか練習し、自分の好みの響きを見つけてみましょう。
まとめ:サスフォーの基礎から応用まで音楽表現を広げるためのポイント
サスフォーコードは、音楽に独自の緊張感や表情を加える便利なコードです。基本的な構成や使い方を理解することで、演奏や作曲の幅が広がります。
さまざまなバリエーションや応用テクニックを身につければ、より個性的で印象的な音楽表現が可能になります。ギターやピアノなど自分の楽器で練習し、実際の曲に取り入れることで、サスフォーの魅力を存分に活かすことができるでしょう。
幅広く使い勝手の良い音、バランスの良い弾き心地を追求した初心者用のエレキギターセット。
色も豊富!まずは音を鳴らしてエレキギターを楽しもう!










